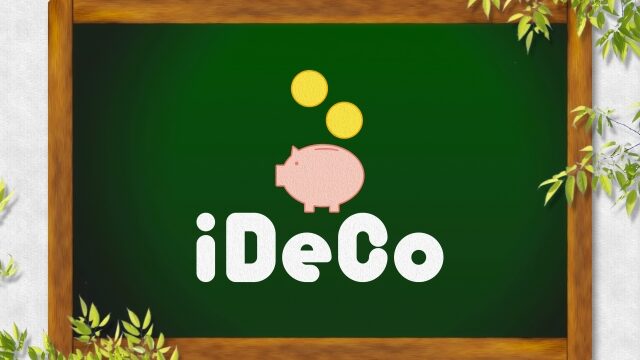シルスプのブログにようこそ
40代、50代の多くは、将来の老後資金のために、
つみたてNISAやiDeCoで頑張って資産形成を続けていることでしょう。
しかし、積立を頑張る「入口」の戦略ばかりに目が行きがちですが、
本当に大切なのは、資産形成の「出口」戦略です。
寿命がわからないのに、大事に育てた「金の卵」を減らしていくのは、
なかなか心の抵抗が大きいものです。

🚨 資産の寿命は「取り崩し方」で決まる
「積み立てた資産を、どうやって取り崩せば、途中で枯渇させずに
長生きできるんだろう?」
「暴落が起きた時、いつ、どれだけ売却すればいいの?」
実は、資産の「取り崩し方」を間違えると、せっかく築いた老後資金が、
思っていたより早く尽きてしまうリスクがあります。
重要なのは、老後の生活費を確保しながらも、
残りの資産には引き続き「働いてもらう」という考え方です。
このブログ記事では、資産形成の総仕上げとなる
「取り崩し戦略」について、「4%ルール」などの基本原則から、
新NISAやiDeCoの賢い活用優先順位まで、
初心者の方にも分かりやすく徹底解説します。
今日から「出口」の準備を始め、安心してリタイアを迎えられる計画を立てましょう。
取り崩し戦略の基本原則:「4%ルール」と資産寿命
資産を取り崩す際に、まず知っておきたい国際的な目安が「4%ルール」です。このルールは、あなたの資産寿命を考える上で非常に重要な指標となります。
💰 4%ルールとは?
4%ルールとは、「年間、資産の4%以内」を取り崩しながら運用を続ければ、資産が30年以上枯渇しない確率が非常に高い、
という経験則に基づいたルールです。
- 前提:
資産を株式と債券などに分散投資し、インフレ調整後のリターンが
4%以上期待できる場合。 - 具体例:
資産が5,000万円ある場合、年間200万円(月々約16.7万円)を
取り崩しても、資産が尽きずに長持ちする可能性が高いとされます。
📈 資産寿命を延ばすための基本
- 取り崩し率を抑える:
4%を超えて取り崩すと、資産寿命は急激に短くなります。
リタイア後は、生活費全体を見直し、4%前後の取り崩し率を
目指しましょう。 - 取り崩し初期の暴落を避ける:
リタイア直後に市場が大きく暴落すると、回復が難しくなり、
資産寿命が縮むリスクがあります(連続の失敗リスク)。
このリスクを避けるための対策が、次の「定率・定額」戦略につながります。
参考文献は、
実践編:失敗しない「定率取り崩し」と「定額取り崩し」
資産の取り崩し方には、主に「定率」と「定額」の2種類があり、
それぞれにメリットとデメリットがあります。
あなたの生活スタイルと市場環境に合わせて選びましょう。
1. 定額取り崩し(生活費を一定に保つ)
毎月決まった金額を取り崩す方法です。
- メリット:
毎月の生活費が安定し、家計管理がしやすい。 - デメリット:
市場が暴落した際にも同じ金額を取り崩すため、
回復期に売却する口数が増え、資産寿命が短くなるリスクがあります。
2. 定率取り崩し(資産寿命を長持ちさせる)
資産全体に対し、毎年決まった割合(パーセンテージ)を取り崩す方法です。(例:4%)
- メリット:
資産が暴落すると取り崩し額が減り、資産が回復すると取り崩し額が
増えるため、資産全体が長持ちしやすい。 - デメリット:
毎月の収入額が変動するため、生活費の管理がやや複雑になる。
| 戦略 | 優先すべき人 | 暴落時の影響 |
| 定額 取り崩し | 毎月の生活費の安定を最優先したい人 | 資産寿命が縮むリスクが高い |
| 定率 取り崩し | 資産寿命を最優先したい人 | 収入が減るが資産の保全性が高い |
【賢い組み合わせ】
生活費の大部分を定額(例:年金+安定資産)、
変動するゆとり資金を定率で賄う「ブレンド型」も有効です。
新NISA・iDeCoの賢い取り崩し優先順位
積立資産を取り崩す際には、税金の仕組みを理解し、
非課税のメリットを最後まで最大限に活かすことが重要です。
1. 最優先:新NISA口座の資産
新NISA口座で運用した利益は、生涯非課税です。
- 取り崩し優先順位:
1番 - 理由:
利益に税金がかからないため、取り崩しによる手取り額が最大化されます。 - ポイント:
NISA枠は売却後も翌年復活しますが、老後の取り崩し開始後は基本的に
非課税枠を減らさないことを意識しましょう。
2. 次点:課税口座(特定口座など)の資産
NISAやiDeCo以外の通常の課税口座は、利益に約20%の税金がかかります。
- 取り崩し優先順位:
2番 - 理由:
NISAの次に取り崩し、最後に税制優遇が強いiDeCoを残すためです。
3. 最後に:iDeCo(イデコ)の資産
iDeCoは、受け取り時にも税制優遇(退職所得控除や公的年金等控除)が
適用されます。
- 取り崩し優先順位:
3番(最後) - 理由:
iDeCoの資産を最後まで残すことで、
老齢給付金として受け取る際の税制メリットを最大限に享受できます。
特に退職所得控除を有効活用するため、受け取り方(一時金か年金か)は慎重に検討しましょう。
大方のかたは、退職所得控除をフルに使うことを考えてらっしゃると思います。
2025年の改正で、 iDeCoの出口戦略が難しくなりました。
以前は、退職所得控除をフルに使えることができました。
「iDeCo」を先に受け取り、5年以上空けて退職金を受け取るケースです。
しかし、2026年1月1日からは、
iDeCoと退職金の受け取りに関する「5年ルール」が「10年ルール」に
変更されます。
ですので、ひとにより戦略がことなるので、
専門家に相談する必要があります。



資産を長持ちさせるための「取り崩し後の運用」の鉄則
取り崩しが始まっても、資産形成は終わりではありません。
資産を長持ちさせるためには、
「取り崩しながらも運用を続ける」ことが不可欠です。
📊 鉄則1:リスク資産と無リスク資産のバランス調整(リバランス)
リタイア後は、暴落の影響を最小限に抑えるため、
生活費3年〜5年分を現金や低リスクの債券などに振り分けておきましょう
(無リスク資産)。
そして、残りの資産は引き続き株式などのリスク資産で運用を続けます。
このリスク許容度に応じて、定期的に資産配分を元の割合に戻す
「リバランス」を行いましょう。
🛡️ 鉄則2:暴落時は「現金クッション」で耐え忍ぶ
取り崩し開始直後に市場が暴落した場合、
含み損が出ている資産を売却するのは避けるのが鉄則です。
- 対策:
前述の生活費3年〜5年分の現金(現金クッション)を取り崩し期間中に
使用し、リスク資産の売却を一時的に停止します。 - 目的:
資産が回復するまで待つことで、暴落時の「連続の失敗リスク」を回避し、
資産寿命を守ります。
🤝 鉄則3:年金との連携を設計する
公的年金の受け取り開始年齢(60歳、65歳、70歳など)と、
資産の取り崩し期間を連携させて考えましょう。
年金受給までの期間を「つなぎ資金」として資産から取り崩す計画を
立てておくと、計画的なリタイア生活が実現できます。
まとめ:出口戦略は「長生き」のための最終計画
資産形成の成功は、いかに効率よく「取り崩すか」にかかっています。
40代・50代の今から「出口戦略」を具体的に
シミュレーションしておくことが、老後の安心につながります。
📌 資産を長持ちさせるための3つの鉄則
- 取り崩し率の厳守:
資産寿命を延ばすために、年間「4%ルール」を目安とした取り崩し率を
守りましょう。 - 賢い優先順位:
税制メリットを最大限に活かすため、「新NISA → 課税口座 → iDeCo」の
順で取り崩すことを基本戦略としましょう。 - 現金クッションの確保:
リタイア直後の暴落リスクに備え、生活費の3年〜5年分を現金で確保
しておき、市場回復を待つための時間稼ぎに利用しましょう。
積立資産は、あなたの努力の結晶です。
適切な「取り崩し方」を身につけ、
資産に仕事をさせながら、不安のない長生き生活を実現しましょう



では、またね~